人気ランキング
ヒカルです。
近所のお花屋さんやスーパーに「七草籠」がありました。
七草かごは名前の通り、「七草粥」に使う七草がそろっている篭です。
1月7日の朝にいただく七草がゆは、体も温まってほっとするお正月あけのお食事ですね。
塩で味付けをしますからあっさりとしていて、消化もよくて胃にやさしい朝食です。
ソラの要望で、七草粥を2-3年前から作っています。
それまではおばあちゃんのおうちで食べたくらいで、ヒカルはあまり習慣としてありませんでした。
ソラが、
「七草粥を食べよう」
といってくれなかったら、何もしないで終わっていたかもしれません。
でもソラの提案によって、日本に残る風習を味わいながら楽しめるひとつの行事になりました。
ソラ、ありがとう。
昨年は近所のスーパーで購入した「七草かゆセット」のパックに入ったものでした。
今年は近所で「七草籠」を見つけたので、それを買ってお水を上げています。
昔は買うというよりも、野の草を摘んで食していたのでしょうね。
東京では土をみかけることは、街路樹のところや花壇、植木鉢くらいです。
おうちの中に小さな自然の姿があるのは、なんだかエネルギーをもらうような愛しい感じになります。
今年はかごから七草を摘んで、七草粥を作ろうと思います。
「災いを除け、長寿富貴をえられる」といいます。
「お正月のごちそうで弱り気味の胃を休める」という日本人の知恵もつまっているようですよ。
6日の夜は、ヒイラギのようなとげがある木の枝を、戸口にはさんで邪気をはらうんですよね。
ひいらぎじゃなくてバラなんていうロマンティックなお花は、邪気をちゃんと払ってくれるのかしら。
七日の朝は、唱えごとをしながら七草を包丁で叩いてお粥を作る。
ちょっとしたストレス発散かしら。
そんなことはありませんね・・・。
平安時代からの風習を新年から楽しみたいと思います。
春の七草というとヒカルは2つの歌を思い出します。
それを紹介して終わろうと思います。
ひとつめは、源氏物語の注釈書「河海抄(かかいしょう)」から。
「せりなずな 御形(ごぎょう)はこべら 仏の座 すずなすずしろ これぞ七草」
七草をそのまま詠んでいるのですが、これを覚えておけば春の七草を間違えずにいうことができます。
それに七草がある姿を想像しながら詠むと、寒い冬の中でも生命の力を感じさせてくれる歌ですね。
もうひとつ。
こちらは古今集に集録されている、光孝(こうこう)天皇の歌です。
「君がため 春の野に出でて 若菜つむ 我が衣手に 雪はふりつつ」
これはご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか?
高校時代の古文の時代に習ったように思います。
若菜は七草を意味していますが、情景が浮かぶうたで心が温まりますね。
古典文学を思い出したヒカルでした。
 |  |  | 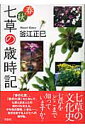 |
¥3990 | ¥460 | ¥2980 | ¥1575 |
 |  |  |  |
¥38500 | ¥150 | ¥1380 | ¥5800 |
 |  |  |  |
¥1260 | ¥9363 | ¥84 | ¥200 |
- PutiRaku - 人気ランキング
・エゾシカ肉のステーキってヘルシーでおいしい!←[前] ・ 春の七草を育てて1月7日に食べよう [次]→・高速もちつきのお餅が食べたい